 |
国のあらましと地図 |
第31回
2006年3月16日(木曜日)はブルンジ
目次
 |
国のあらましと地図 |
★
| 独立-1962年 国名-ブルンジ共和国 Republic of Burundi 面積-3万平方キロメートル 人口-730万人(2004年) 主な言語-フランス語、キルンジ語、スワヒリ語 |
★
自然
| 西部にアフリカ大地溝帯が走り、タンガニーカ湖の北東岸があります。その東側は断崖になり、高原が続きます。 降水には恵まれていますが、人口密度が高いこともあって、森林伐採で土壌浸食が進んでいます。 (右の写真は、2005年愛知万博の展示から) |
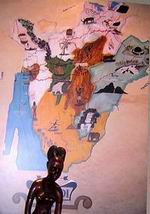 |
★
歴史
| 15世紀にブルンジ王国が成立 | 紀元前は、さまざまな言語を話す人たちが住んでいましたが、バンツー系言語を話す人が生産力を拡大して、その言語文化が支配的になってきます。 そこから、農耕、あるいは牧畜に重きをおいた集団が現れてきます。 15世紀、ブルンジ王国が成立。 |
| ドイツ領ルアンダ・ウルンジを経て ベルギー領になります |
1885年、ドイツの勢力下に入ります。 90年、ドイツ領東アフリカの一部となります。王の権限は保たれた間接統治が行なわれます。 99年、現在のルワンダ(当時の呼称はルアンダ)と統合、ドイツ領ルアンダ・ウルンジに。 第1次世界大戦中にベルギーが占領し、1923年からベルギーの国際連盟委任統治領。第2次大戦後、ベルギーの国際連合信託統治領。ウルンジとルアンダは別々の自治権を認められます。 61年、国連監視下の選挙で、ルワガソレ王子が率いる国民統一進歩党(UPRONA。後に再組織)が勝利し、王子が首相に就任(国連が合体しての独立を希望していたルワンダでは、共和派が議会で多数)。その後、王子は民主キリスト教党指導者により暗殺されます。 |
| 1962年、王国として独立 66年、クーデターで共和制に |
62年、ブルンジ王国として独立。 66年、皇太子が、国外で療養中の王を廃位し、即位。ミコンベロ大佐を首相に任命。 同年、首相によるクーデターで、国王を追放。共和制を宣言。UPRONAを唯一の政党とします。 72年、フツによるクーデター未遂事件から、フツとツチが衝突。フツが難民となって逃れ出ます。 76年、バガサ大佐によるクーデター。 87年、ブヨヤ大佐によるクーデター。 88年、北部でフツが大量虐殺。 |
| 1993年から10年間 実権を握る国軍とゲリラ組織の間で 紛争が続きます |
92年、複数政党制を含む新憲法を採択。 93年、複数政党制の下の総選挙で、野党、ブルンジ民主戦線(FRODEBU)が勝利。フツ初のヌダダイエ大統領が選出。国軍改革をめぐって、軍と対立。軍により大統領が暗殺され、これを契機に内戦が始まり、反政府勢力と国軍との戦闘、民間人の虐殺が続きます。 94年、国民議会は新大統領として、ンタリャミラを選出。ンタリャミラ大統領とルワンダ大統領が乗った飛行機が撃墜されて、両大統領は死亡。ヌティバントゥンガニャ大統領選出。 96年、軍部クーデターによりブヨヤ元大統領が大統領代行に就任。アルーシャにおいて、和平会合開催。紛争当事者間で、敵対行為の停止に合意。 98年、ブヨヤ暫定大統領就任 2000年、アルーシャ和平合意。 2001年、暫定政府が成立。前半の大統領に、ブヨヤが就任。 2003年、後期の大統領に、ヌダイゼイエが就任。暫定政府と最大のフツ系武装勢力、CNDD-FDD間で和平合意署名。 2005年、新憲法を国民投票により採択。国民議会・上院議員選挙を実施。CNDD-FDDが勝利。その後の間接選挙で、CNDD-FDDの代表、ンクルンジザが大統領に選出されます。 |
★
産業・経済
| 農業国で、食糧作物としては、キャッサバ、バナナなどを生産。93年までは食糧は自給できていましたが、内戦勃発以降は食糧援助に頼っています。人口密度が高く(230人/Km2。サハラ以南のアフリカ諸国の平均値は約229人)、内陸国という地理的制約もあります。 主な輸出産品は、総額の約8割を占めるコーヒー(高品質のアラビカ種)と、2割弱の茶(1999年)。 主な輸出相手国は、ドイツ、米国、ベルギー、ケニア、ルワンダ。 主な輸入品は、半加工品、資本材、消費材。相手国は、ベルギー、ケニア、フランス、タンザニア、インド(2003年)。 |
★
この本で読む
独立直後のブルンジとルワンダ
| 服部正也 著 『ルワンダ中央銀行総裁日記』 中公新書 1972年 |
| 著者(1918~1999年)は、1965年、日本銀行から、ルワンダ中央銀行総裁として、国際通貨基金技術援助計画に出向。1971年まで、ルワンダの経済再建を行ないました。 「第Ⅱ章 ヨーロッパと隣国と」に「ブルンディ出張」が記されています。「旧ルワンダ・ウルンディ発券銀行の清算委員会の会合に出席」するためでしたが、「平価切下げ」の調査などの目的がありました。 ブジュンブラの町を見た筆者は、「キガリとの差を痛感」します。「ホテルは数軒ある。料理屋も本格的なフランス料理を食べられるのが3軒ある。映画館も数軒ある。商店らしい商店が並んでいて品物も豊富で、お客もたくさんいる。本屋も2軒ある。当時人口15万といわれたこの町は道が舗装されており、きていな住宅が湖の東岸の岡に並んでいる。港も立派だ」 一番うらやましいと思ったのは、「3階建ての立派なブルンディ王国銀行の建物」そして「ブルンディ人行員」の服装であり、仕事ぶりです。ルワンダ中央銀行のほうは、薬局を改造した建物で、総裁公室の事務机の引き出しの鍵はこわれているという状況でした。 職員は、ほとんどが旧ルワンダ・ウルンディ発券銀行からの職員、十数人は旧ベルギー領コンゴ・ルワンダ・ウルンディ中央銀行時代からの職員で、フランス銀行からの出向、旧ベルギー領コンゴ・ルワンダ・ウルンディ中央銀行時代からといった外人職員が14人がいます。 「生みの悩み」に苦しむ新設のルワンダ中央銀行に対して、ブルンディ王国銀行は、「組織と伝統が確立」されているという、「町の差を超えた」大きな差を知ります。 フランス銀行から出向している総裁と、平価切り下げの話をしているうちに、政府は「国際収支対策以上に考えていない」ように思い、政府の態度について質問をします。 「政府の人たちは政争にあけくれして経済のことはベルギー人顧問のいうなりですよ」 筆者は外人商社の人にも会います。独立前から存在するそれらの会社は、ルワンダのキガリやブタレにも店を出しています。それらは、「独立後、ルワンダ政府の歓心を買うため」ルワンダ法人になっていますが、「実質は独立前と同様」に「ブジュンブラ本社のあわれな出張所にすぎない」と知ります。 |
ご意見・感想・情報をお寄せください。
Eメール mokuyobi@tam2.co.jp